ひとむれ
このコーナーでは、家庭学校の月毎の機関誌である『ひとむれ』から一部を抜粋して掲載しています(毎月上旬頃更新予定です)。
職員が、家庭学校を通じて感じたことや伝えたいことを表しています。是非、ご感想をお聞かせください。
※都合により『ひとむれ』本誌と内容が異なる場合がございます。ご了承下さい。
再非行
小さな手
校長 加藤正男
カシワの木に枯れ葉が落ちず残っています。若い芽をまもるため、大きなカシワの葉は、枯れながらも、木にとどまっているのです。きびしい寒さが続きました。マイナス20度を超える日です。雪道は太陽の光を浴びて光っています。三学期の始まった本館校舎の廊下の温度はマイナス10度になることもあります。教室は暖房で温まりますが、トイレは電気暖房をしていても、手洗いの蛇口はつららができ、止まります。
雪も、かなり多く、物置小屋の屋根の上は、60センチぐらいの高さに積もっています。
1月16日から20日までの五日間、遠軽駐屯地の自衛隊員の5名のスキー指導員を迎えて、神社山のスキー学習がはじまりました。今年は12月の早い時期から降雪があり、年末、新年と厳しい寒さも続き、神社山のスキー場はいいコンディションとなっています。地元のスキー場より雪の状態がいいと言ってくれます。釧路や帯広地区の生徒は、スケートについては学校で教わり得意だがスキー学習は初めてとのことですが、初めてのスキーながらも午前中の二時間ぐらいで基礎ができるようになります。午後からはロープリフトを使っての滑走です。思うように山に登って行けず苦労していますが、「楽しい」との声が上がります。最終日は遠軽町のロックバレースキー場でのスキー検定試験です。参加者全員が、ジュニア3級から級別2級まで、それぞれ級に合格しました。
スキー学習をもう一回やりたがっていたA君は、昨年の終わりに復学のため地元に戻りました。三学期がスタートして4日目、担当の児童相談所の先生から、よい知らせが入ってきました。戻ったクラスの中で学習に前向きに取り組み、家庭学校での生活体験を生かして成長が著しいとの電話です。入校したころ、何か面白そうだからと無断外出を一緒にしていました。すぐ人に流されて問題行動を起こしてしまう、と入校前の課題そのものの行動でした。家庭学校での生活が活かされるよう、春からの生活がA君にとっていい方向に進みますよう祈りつづけて行きたいのです。
年末の帰省で34名とほとんどの生徒が保護者のもとに戻っての生活ができました。
家庭学校の卒業生のゆくえについて「教育農場五十年」留岡清男著の中で丁寧な動向調査とその分析結果が書かれています。留岡清男先生の学友で、戦後家庭学校の嘱託の医師として生徒たちと関わって頂いた奥田三郎先生を中心にその全生涯を家庭学校につくした、鈴木良吉、横山義顕、寺崎好、大泉栄一郎、岸本種次の諸先生方との共同研究によりまとめられています。大正3年から昭和39年3月31日までに988名の生徒を迎え、905名の卒業生のゆくえです。
概括(ページ236)として
一 出身家庭の経済状況は、あまり予後に影響しない。
二 知能の程度が高い方が、よりよい予後成績を上げる傾向が認められるが、知的に低くても成功している者も少なくない
三 情意の一つとして、積極性を示す者の方が、予後成績は良好の可能性が高い。
四 不良化をもたらす要因一つとして、純環境的に、すなわち家庭外環境条件がわるくて不良化したと思われるものは予後は非常によく、教護教育は成功している。これに反して、本人の素質が問題となるものでは予後成績がよくない傾向にある。
五 卒業事の支持条件が十分で有るほど、予後成績の向上が期待され、支持条件不良の場合には、予後成績が低下する傾向のあることが、明白に認められる。
まとめで指摘されたことに家庭学校では常に留意しながら、運営がなされその後、1300人の卒業生を送り出しています。一人ひとりの卒業生が、ここでの生活を土台としてさらに自らの気づきを重ねながら、より幸せな生活へと進むことを願い続けているのです。
(元原稿から一部分をカットして文章を掲載しています。ご了承ください。)
千葉正義
雪も降り積もった寒い冬の日のことである。ある寮の寮長が児童の通院で不在だったため、その寮の寮生と一緒に下校した時、その中の小学生の子が、「先生の手ってあったかいですね。」と言って私の手を握ってきた。私は、「○○は甘えんぼだな。」と言うが、その子は照れくさそうに、「違いますよ、ただ寒いからですよ。」と言い、握ったその手を離そうとはしない。寒空の中、そっと握りしめたその手は確かにとても冷たく、そして小さかった。
その子は一昨年の秋に入校してきた。子どもらしい屈託の無い笑顔が愛らしく、だが、当時から状況を問わずしつこくまとわりついて来るのが印象的な子だった。すれ違いざまに背中を叩いたり、わざと足を踏んで来たりと自分からちょっかいをかけてくるので相手にしてやるのだが、やりすぎるとむくれてしまう。そんな状況故に周囲の子とトラブルになることも多かった。正直扱いにくい子だなというのが最初の印象で、自分の機嫌の良い時だけベタベタとまとわりついて来るのを私は良いことと思っていなかった。
以前こんなことがあった。お昼の給食の時間に味噌汁を運んでいた私に対し、後ろから急にしがみついてきたのである。幸い転倒はしなかったが、その時私は激しく叱責した。その後彼は私と接するとき、少し距離を取るようになる。寮担当職員が休みや出張等で不在の時など、代わって私が留守を預かる機会があるのだが、その時も、反抗するというわけでは無いのだが、以前のような愛らしい笑顔はあまり見られず、ただ淡々と日課をこなしているだけのように思えた。
そんな彼も日々の生活の中で少しずつだが成長してきている。以前は嫌なことから逃げてばかりいたが、やれることも増えてきた。注意されるとふてくされてそのまま固まってしまうことも多かったが、その時間も少しずつ短くなってきた。ある時、こんなことを言っていたことがある。「寮でたまに先生と一緒にお風呂入ってるんですよ。」笑顔で話す彼はやはりどこか照れくさそうで、でも嬉しさを隠せない様子だった。その時、私は初めて気付いたのだった。
「この子は甘え方を知らない」
家庭学校には親の愛情を知らない子が多い。入所児童の資料を見ると、そこには目を覆いたくなるような過去が事実として書かれていることも少なくない。小中学生となると、まだまだ親の愛情が必要な年頃であるに違いない。手をつないだり背中にしがみついて来たりするのは、それは本来もっと幼いころに経験しているはずであるが、それが乏しいので今どうやって関わったら良いのかがわからないのだ。あの日給食のときも彼は、転倒させてやろうとか悪意を持って私に対ししがみついたのではなく、きっと軽い悪戯のつもりでそれをきっかけに私と関わりを持ちたかったのだと思う。しかし、あの時の私は何も考えずにただ彼のとった行動のみをみて叱った。何が悪いのか、どうして良くないのかを理解させてあげることが出来ていなかった。彼にとっては非常に辛い思いをしたのではないかと今改めて思う。
それからは私は彼との関わり方を変え、寮の留守の時など遊ぶときは目いっぱい遊ぶようにした。もちろん間違った行動があれば叱ることもあったが、ただ叱るだけではなくなぜ良くないのかを明確に伝えるようにした。すると最初の頃はふてくされてばかりだった彼が、ある日「さっきはすいませんでした。」と自分の口で言えるようになったのである。恐らく、普段自分の生活する寮では当たり前にやれていることだと思うのだが、普段と違う環境でそれが出来るようになったのは大きな成長であると思う。また、最初の頃のように状況を問わずまとわりついて来るのではなく、自由時間にテレビを見ていると隣に座ってきたり、校内を歩いていると手をつないできたりと甘えることに対し素直になってきたのも彼にとっては成長だと思う。私はそんな時は思う存分甘えさせてあげるのも大事なのかなと思うようになってきた。
だが、いつも甘えさせることが功を奏すとは思わない。子どもは逃げ道を探す。私はフリー職員(家庭学校では寮担当以外をこう呼ぶ)であるため、寮での生活の様子は寮長に聞かなければ見えない部分も多い。また、分校の先生方から聞く学習中の態度も大事である。例えば寮での生活状況が悪かったり、授業中の態度が悪い等で何らかの指導を受けているときに、私だけ違った指導をするとそれが子どもの逃げ場となり、本来必要な指導が入らなくなってしまうことも考えられる。精神的に未発達な子どもが楽な方へ逃げるということは、家庭学校に入所している子たちに限らず当たり前のことだと思う。子どもとは本来親の姿を見て育つのである。しかし、施設に入所している子にとっては、その逃げ場となる状況を身近にいる大人である私たちが作ってしまうこと、本来のその子の持つ課題が見えなくなってしまうし、一度楽することを覚えさせてしまうと元に戻すのは難しい。だからこそ、時には厳しく突き放すことも大事なことだと私は思う。「甘えさせる」ことと「甘やかす」ことは違うのである。ちょっとした関わり方の間違いが、その子の将来をも左右する取り返しのつかない大きな間違いとなってしまうこともある。私たちは、それを頭において子どもと向き合っていかなければいけないと思う。
この原稿を書いている今日は、小学生は予防接種があり私が引率した。甘えんぼうの彼は、久しぶりに校外に出られたことが嬉しいのか、少しはしゃいでいる。「ほら、行くぞ」と言って手招きした私の手を、精一杯ギュッと握ってくる。やっぱりその手は小さかったが、以前よりほんの少しだけあたたかく感じた。今、彼はどんな思いで私の手を握っているのだろう。これからも色々なことを経験して、どんどん大きくなっていくのだろう。そして、いつの日か私の手を握るこの小さな手が自分の子供の手をやさしく包み込む大きな手に、絶対に離すことのないあたたかい手になって欲しい。私は、そんなことを考えながら歩いていた。
(元原稿から一部分を変更して掲載しています。ご了承ください。)
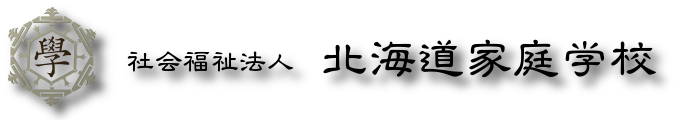
 トップページへ
トップページへ